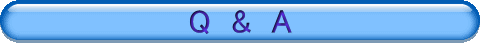
前のページへもどる
Question
- ”N&H”って、どういう意味ですか?
- 「高真空N&H工法」って、どんな工法ですか?
- どんな特長がありますか?
- 特許の内容はどういうものですか?
- マニュアルのようなものはありますか?
- 施工実績はどれくらいありますか?
- どんな地盤に適用できますか?
- 苦手な地盤はありますか?
- 高真空N&H工法を設計するには、どんな土質調査が必要ですか?
- どれくらいの深さまで改良できるんですか?
- 一度に改良できる広さはどれくらいですか?
- 改良後の地盤は改良前と比べて土性がどう変わるのですか?
- 改良後の地盤はどれくらい強度が上がりますか?
- 改良後の強度は、どうやって調べるんですか?
- 沈下量はどうやって計算するのですか?
- 圧密沈下時間はどうやって計算するのですか?
- 残留沈下量を少なくできるんですか?
- 盛立速度はどれくらい速くできるのですか?
- 盛土の安定については、どのように考えるんですか?
- どんな材料を使っているんですか?
- 保護シートは何のために必要なのですか?
- 使用した材料は撤去できますか?
- 気密シートや保護シートは転用できますか?
- 鉛直ドレーン打設機は特殊なものですか?
- 気密シートを破損させないために、注意すべき点はありますか?
- 周辺地盤の沈下等の影響はないのですか?
- 真空駆動装置の稼働時間は1日24時間ですか?
- どんな計測が必要ですか?
- 計測には特殊な計器を使いますか?
- 施工管理はどのように行いますか?
- 盛土時の施工管理はどうするんですか?
- 真空ポンプを止めたらリバウンドしませんか?
- 設計沈下量と実績沈下量(観測値)はどう違いますか?
- 排水量と沈下量は同じくらいですか?
- コスト(単価)はどれくらいですか?
[UP]
Anser
- ”N&H”って、どういう意味ですか?
- "reNewal and Hi-quality"の"N"と"H"です。
- 「高真空N&H工法」って、どんな工法ですか?
- N&H工法は改良型真空圧密工法とも呼ばれています。真空圧密工法は、大気圧工法とも呼ばれていました。
- 真空圧密工法は、1950年ごろ発明され一時取組まれましたが、効率が悪く一般に広く普及しませんでした。近年、気密シートやドレーン材などの材料における技術の進歩によって、確実に真空圧が作用し地盤内の減圧ができるようになりました。これが、N&H強制圧密脱水工法です。
- 他の工法に比べて経済性に優れ、短工期、環境にやさしいなどが顧客ニーズに合ったことで、注目されるようになりました。
- 鉛直ドレーンを利用した真空圧による強制脱水(排水)により、深部まで減圧効果が及び圧密が進行します。これまでの圧密促進工法と同様で圧密による沈下や強度増加が図られます。
- どんな特長がありますか?
- 高真空圧がドレーン材を通じて、改良対象地盤全体に継続的に作用するため、バラツキの少ない均質な地盤改良ができます。
- すべり破壊に対する安全性に優れるため、急速盛土施工が可能となり、工期短縮・工費縮減を図ることができます。
- セメントなどの固化材を使用しない、環境にやさしい工法です。
- 特許の内容はどういうものですか?
- 概ね次のような内容からなります。
- 鉛直ドレーン材、通水材(水平ドレーン材)、気密シートの各工程と真空ポンプで負圧の状態を作り出す工程とからなることを特徴とする軟弱地盤の改良方法及び改良装置。
- 間欠的に作動させることにより効率よく減圧できる。
- 盛土と併用することができる。
- 気水分離システムによる高真空圧の維持。
- マニュアルのようなものはありますか?
- 真空圧密技術協会では、①パンフレット、②技術資料、③積算資料などを取り揃えています。
- 施工実績はどれくらいありますか?
- 協会設立(1999年4月)後の施工実績は、2004年12月現在で65件(約332万m3)です。
- どんな地盤に適用できますか?
- 未圧密、正規圧密状態の粘性土の軟弱地盤や腐植分の混じった軟弱地盤が適用性の高い地盤です。
- 泥炭、高有機質土のような高含水比、高圧縮性の土では特に有効です。
- 浚渫土などの高含水の土砂にも適用できます。
- 苦手な地盤はありますか?
- 表層部に砂層が厚く堆積している地盤や通気性の高いガラなどを含む埋土層がある地盤です。
こんな場合には、気密シートの端部を深くまで埋め込むことなどの特殊な対応が必要です。
- 過圧密地盤も改良効果が大きくは期待できません。
この場合、載荷盛土を併用して荷重を加えてやることで対応できます。
- また中間に厚い砂礫が分布したり、中間あるいは基底の礫層が被圧地下水を有している場合には、別途遮断工法を併用するなどの検討が必要です。
- 高真空N&H工法を設計するには、どんな土質調査が必要ですか?
- 基本的には、通常の軟弱地盤で実施される程度の土質調査が必要です。
- まず地形状況、土層構成や分布、地下水位や被圧状況がわかっている必要があります。
- また、一般的な物理試験のほか、一軸圧縮試験や三軸圧縮試験、圧密試験が必要です。
- どれくらいの深さまで改良できるんですか?
- 鉛直ドレーンが打設可能な深さまで改良可能と考えています。
- 施工実績の最大施工深さは、GL-30.5mです。
- 一度に改良できる広さはどれくらいですか?
- 1セットの施工ブロックは3000m2が標準ですが、全体の面積には上限はありません。
- 工期との関係で施工機械のセット数を決めることになります。
- 改良後の地盤は改良前と比べて土性がどう変わるのですか?
- 密度(単位体積重量)や強度が増加し、含水比や間隙比が低下します。
- 改良後の地盤はどれくらい強度が上がりますか?
- 通常の圧密促進工法と同様、圧密の進行とともに強度増加します。
- 実績では、真空載荷方式(高真空N&H工法単独)による改良では、地盤の粘着力は20~30kN/m2程度まで上がります。
- 真空盛土方式(載荷盛土との併用)では、盛土厚10m前後の場合で、粘着力が50~100kN/m2と原地盤の強度の約5倍の強度増加が確認されている例もあります。
- 改良後の強度は、どうやって調べるんですか?
- 真空載荷方式(高真空N&H工法単独)では、コーン貫入試験やボーリング調査による土質試験を実施します。
- 真空盛土方式(載荷盛土との併用)では、地盤がかなり硬くなるのでボーリング調査による土質試験を実施します。
- 沈下量はどうやって計算するのですか?
- 沈下量はバーチカルドレーン工法の設計手法と同様
①e法、②mv法、③Cc法を用いて計算します。
- 設計では、真空載荷圧としては、鉛直ドレーン打設深度まで△p=70kN/m2の荷重が作用されるものと考えて計算します。
- 圧密沈下時間はどうやって計算するのですか?
- 設計では、通常の圧密計算と同様、バロンの式で計算します。
- 残留沈下量を少なくできるんですか?
- 真空載荷荷重をサーチャージ荷重として利用することにより、残留沈下量を減らすことができます。
- 真空載荷荷重は、65kN/m2~90kN/m2ですが、設計では70kN/m2と考えます。盛土高さにすると3~5m分に相当します。
- 盛立速度はどれくらい速くできるのですか?
- 高真空N&H工法を併用して急速盛土をする場合、施工実績では約20cm/日で盛土できています。
- 設計時は、通常の軟弱地盤であれば15~20cm/日を目安としています。
- 盛土の安定については、どのように考えるんですか?
- 真空圧密工法を併用して道路盛土を立ち上げる場合、真空圧による減圧作用で、過剰間隙水圧の発生を抑制できることが盛土の安定に寄与します。
- 圧密に伴う強度増加や真空圧の作用による過剰間隙水圧の消散を考慮した円弧すべり計算で検討することが出来ます。
- どんな材料を使っているんですか?
- ドレーン材、集水管、気密シートは、この工法用に開発した材料を使用しています。
- 鉛直ドレーンには、プラスチックボードドレーンの一種で、アーパスドレーンと呼ばれています。
プラスチックネット入りの不織布(幅10cm)で作られたものであり、目詰まりがしにくく濾過能力の高いドレーン材です。
- 水平ドレーン材は、鉛直ドレーンと同じタイプで、幅30cmのものです。
- 有孔集水管は、塩ビの有孔管(VP-65)に目詰まり防止用に特殊フィルターを巻いたものを使用します。
- 特殊フィルターは30cm幅のアーパスドレーンであり、水平ドレーン材と同規格のものです。
- 送水管は、塩ビ管(VP-65)を使用します。
- 気密シートは、ピンホールが発生しにくい二層構造の塩化ビニールシートで、厚さは0.5mmです。
- いずれも、他の材料では、施工実績がありません。
- 保護シートは何のために必要なのですか?
- 地表に石などの突起物があると、気密シートに穴があき、漏気すると真空圧が上がらなくなってしまいます。
- 気密シートに穴があくのを防ぐために気密シートの下に、保護シートを敷設します。
- 保護シートには、ドレーン材と同じ不織布でできている、厚さ1mm~3mmのものを使用していますが、気密シートに穴が開くことが防げるものならば代用できます。
- 使用した材料は撤去できますか?
- 鉛直ドレーンは、基本的には撤去できません。
- 水平ドレーンや集水管、気密シート、保護シートは、真空単独載荷の場合には、施工後撤去することができますが、盛土併用の場合には、埋まってしまうため撤去することができなくなります。
- 気密シートや保護シートは転用できますか?
- 気密シートや保護シートの再利用は品質の問題から出来ません。残念ながら一度使った材料は産廃として処分します。
- 鉛直ドレーン打設機は特殊なものですか?
- 気密シートを破損させないために、注意すべき点はありますか?
- 盛土を併用する場合には、気密シート直上に撒き出す盛土材には鋭角な尖りをもたない土砂を用いると良いでしょう。
- 場合によっては気密シートの上に保護シート(不織布)を敷設する等の配慮をしてください。
- 周辺地盤の沈下等の影響はないのですか?
- 周辺地盤への影響が皆無とはいえません。
- 実績では、沈下の影響範囲は1D(D;軟弱地盤への鉛直ドレーン打設長)程度の場合が多いようです。
- 改良境界で中央部最大沈下量Smaxの0.5~0.9Smax程度の沈下が生じた例もあります。
- このとき、横方向変位は0.2~0.4Smax程度の引きずり込みを生じています。
- 表層部や中間層に砂層や腐植土(繊維質)がある場合には沈下の影響範囲が2D~3Dに及ぶことも予想されます。
- 真空駆動装置の稼働時間は1日24時間ですか?
- どんな計測が必要ですか?
- まず、真空駆動装置の運転管理用に①真空駆動装置圧力、②気密シート下圧力、③排水量、④排水温度は必ず計測します。
- また通常は、品質管理のために、⑤地表面沈下量、⑥地中間隙水圧を計測します。
- 必要に応じて、⑦層別沈下量、⑧地表面変位量、⑨地中変位量、⑩周辺地下水位などを計測します。
- 計測には特殊な計器を使いますか?
- 概ね、一般の圧密促進地盤改良工法で用いられる計器と同様です。
- ただし、間隙水圧計については、負圧側の変動も確認できる特殊なタイプの間隙水圧計を用います。
- 沈下量測定については水盛式沈下計を一般に用います。
- 施工管理はどのように行いますか?
- 運転管理および標準的な計測管理項目については、施工管理システムによって、計測データを自動的に記録します。
- リアルタイムな計測データをもとに安全で確実な施工管理ができます。
- 盛土時の施工管理はどうするんですか?
- 真空ポンプを止めたらリバウンドしませんか?
- 条件によってリバウンド量の多少はありますが、これまでの実績からは問題となるような大きなリバウンドは発生していません。
- これまでの事例では数mm程度です。
- 設計沈下量と実績沈下量(観測値)はどう違いますか?
- 高真空N&H工法に限らず、軟弱地盤の圧密沈下量は、多くの場合、設計値と実測値に差があります。
- 動態観測によって実際の沈下量を計測して設計・施工へフィードバックすることが大切です。
- 排水量と沈下量は同じくらいですか?
- これまでの施工実績では、いずれの現場でも沈下体積以上の排水量が観測されています。
- 特に中間砂層などがある場合は、周囲から水、空気を引っ張ってくるため、沈下量に比べ排水量が大きくなる傾向があるようです。
- コスト(単価)はどれくらいですか?
- 条件によって違いますが、直工費は、概ね1,000円/m3~2,000円/m3 です。
- 改良深度が10mで、施工規模が10,000m2という条件で試算すると、約1,500円/m3になります。